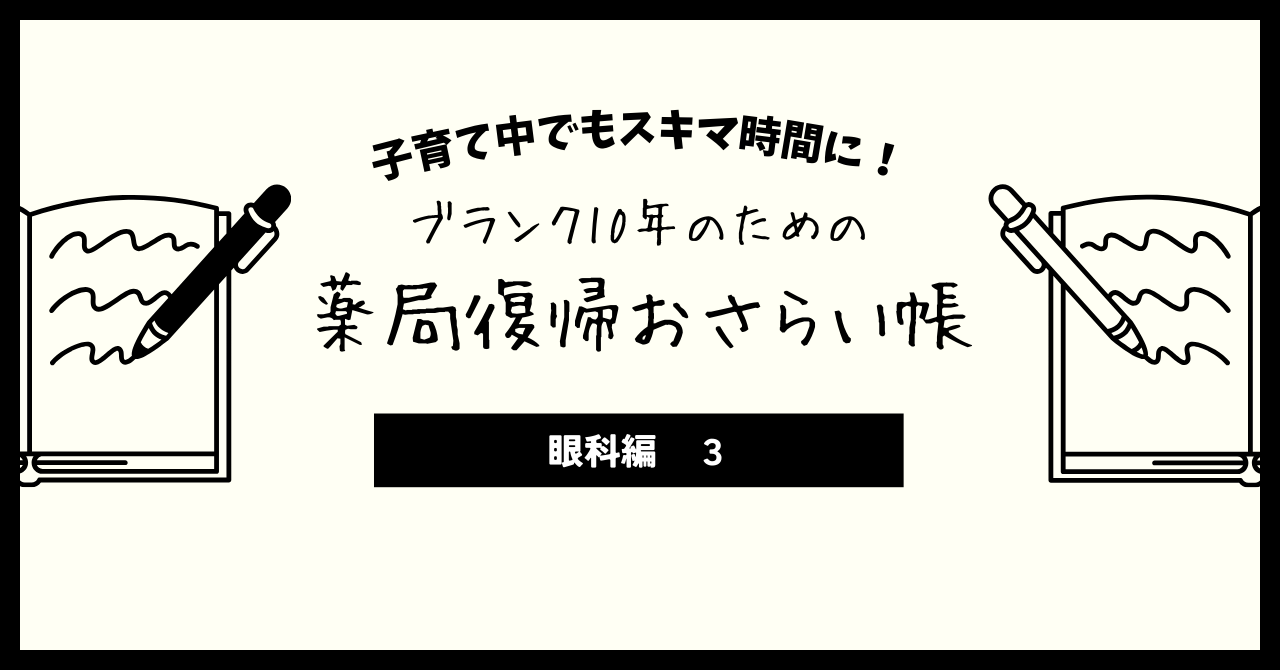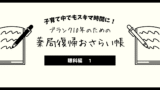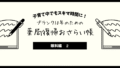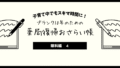「もう一度、薬剤師として働きたい」
そう思っていても、10年という長いブランクを前に、なかなか最初の一歩が踏み出せないでいるママ薬剤師さんへ。
「近所の薬局で働きたいけど、眼科の処方をうけてるみたい…」
「経験ないし眼科の処方箋って難しそう…」
「昔勤めてたけど最新の薬は全然知らない…」
こんな漠然とした不安で、復職を諦めかけていませんか?
大丈夫です。
この「子育て中でもスキマ時間に! ブランク10年のための薬局復帰おさらい帳」シリーズでは、その不安を一つずつ一緒に乗り越えていきます。
忙しい子育ての合間を縫って、最短で現場復帰を目指すママ薬剤師のための復習講座です。
【眼科編】では、現場でよく出る薬と服薬指導のコツに絞って解説します。
- 緑内障について病態や処方薬、服薬指導のコツ
今すべてを網羅する必要はありません。
効率的に知識を学び、自信を持って面接や復職に臨みましょう!
さあ、今日から一緒に、未来の自分に自信をつけていきましょう。
「ブランクが長いから復職が不安…勉強に身が入らない!」ママ薬剤師さんならこちら↓
復習を始める前に!最短で復帰するための行動プラン
さあ、眼科の門前薬局に応募は済ませましたか?
最短で復職を果たすには、勉強を始める前に、まず「行動」を起こすことが大切なんです。
私は、「転職サイトで眼科の門前薬局の求人に応募し、面接日を1〜2週間後に設定する」ことをお勧めしてます。
なぜかと言うと、「期限」を設けることで、復習の効率が格段にアップするからです。
漠然とした「いつかやろう」が、「面接までにこれを覚えよう」という具体的な目標に変わります。
このゴール設定が、あなたのやる気を盛り上げ、現場ですぐ使える知識に絞って効率よく学べるようにしてくれます。
まだ応募をしていないなら、さっそく気になる求人を探して応募してみましょう。
緑内障の処方箋が怖くない!知識と服薬指導のポイント
眼科門前では、なかなかに頻度が高い緑内障。
生涯にわたる治療が必要なため、患者さんとの信頼関係を築くことが大切です。
まずは薬と病気の基本を抑え、自信を持って患者さんと向き合えるようにしましょう。
緑内障の基本:病態をサクッと理解
緑内障は、眼圧(目の硬さ)が高くなり、視神経を圧迫して視野が徐々に狭くなる病気です。
一度失われた視野は元に戻らないため、生涯にわたる継続的な治療が非常に重要です。
正常眼圧は10~21mmHg。
ベースライン眼圧(治療を開始する前の眼圧)から、20~30%以上の眼圧下降を目指すのが一般的です。
眼圧が正常範囲内でも視野障害が進行するタイプの緑内障もあり、正常眼圧緑内障と呼ばれ日本人に最も多いタイプです。
現場でよく見る緑内障の薬と使い分け
現在の緑内障治療の現場では、まず第一選択薬であるプロスタグランジン製剤(キサラタン、タプロス、トラバタンズなど)が単独で処方されます。
効果が不十分な場合は、2種類目・3種類目と追加あるいは種類を変更して目標眼圧を目指します。。
点眼薬による眼圧のコントロールが難しい場合に、レーザー治療や手術が検討されます。
まずは点眼剤を復習するだけで十分です。
点眼剤にはたくさんの種類があるように見えますが、作用機序で分類すればシンプルです。
サッと読んで、「うんうん、あったな、この薬!」と思い出していく感じで大丈夫です。
プロスタグランジン関連薬
- 代表的な薬:
- キサラタン(ラタノプロスト)
- ルミガン(ビマトプロスト)
- タプロス(タフルプロスト)※タプロスミニ(防腐剤を含まないのでドライアイ患者によい)
- トラバタンズ(トラボプロスト)
- レスキュラ(イソプロピルウノプロストン)1日2回
- 用法用量: 基本的に1日1回1滴点眼。
- ポイント:
- 房水(目の中の液体)の排出(ぶどう膜強膜流出路)を促して眼圧を下げる。
- 一日一回の点眼で、患者さんの負担が少なめ。
- 副作用として、まぶたや虹彩の色素沈着、まつ毛が伸びる。点眼後洗顔するとよい。
- 最も眼圧を下げる効果が高いので、最初に使うことが多い。
β遮断薬
- 代表的な薬
- チモプトール(チモロールマレイン酸塩)、リズモンTG(熱応答ゲル1日1回冷蔵保存)
- ミケラン(カルテオロール塩酸塩)など。
- 用法用量: 基本は1日2回1滴
- ポイント
- 房水の産生を抑えて眼圧を下げる。
- 気管支喘息や心臓疾患のある患者さんには使えない場合がある。
- ベータ遮断薬、抗不整脈薬は併用禁忌
- テノーミン(アテノロール)、セロケン(メトプロロール)、インデラル(プロプラノロール)、アーチスト(カルベジロール)など
- ワソラン(ベラパミル)、ヘルベッサー(ジルチアゼム)、ジゴシン(ジギタリス製剤)など
- 内服薬や持病について医師に伝えたか&薬局でも必ず内容確認
配合剤
- 代表的な薬
- タプコム(タフルプロスト/チモロールマレイン酸塩)
- ザラカム(ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩)
- ミケルナ(カルテオロール/ラタノプロスト)
- デュオトラバ(トラボプロスト/チモロール)
- コソプト(ドルゾラミド/チモロール)1日2回
- アゾルガ(ブリンゾラミド/チモロール)1日2回
- アイベータ(ブリモニジン/チモロール)1日2回
- アイラミド(ブリモニジン/ブリンゾラミド)1日2回
- 用法用量: 1日1回1滴点眼。
- ポイント:
- 単剤よりも高い眼圧降下作用が期待できる。
- ベータ遮断薬単体より点眼回数が減るものもあり、アドヒアランス(服薬遵守)がアップ。
- 併用薬・持病(心臓・不整脈・喘息)・医師に伝えたか、を確認すること
その他
- 炭酸脱水素酵素阻害薬:トルソプト(ドルゾラミド)、エイゾプト(ブリンゾラミド)
- 1日2~3回1滴点眼。
- 房水の産生を抑え、眼圧を下げる。
- 点眼後に口の中が苦く感じる副作用がある。
- 薬剤に特有の強い苦味があり、鼻や口に流れることで苦み→「問題はない」と伝える
- すぐ瞬きをせず、一分ほど目をとじておく
- 点眼後目頭を指で押さえる
- 苦みがあれば口をゆすぐ
- α2作動薬:アイファガン(ブリモニジン)
- 1日2回1滴点眼。
- 房水の産生を抑え、ぶどう膜強膜流出路からの房水流出を促進。
- 眠気やめまい、血圧低下などの副作用に注意。
- 高齢者への処方では、点眼後の様子を尋ねてみる。
- ROCK阻害薬:グラナテック(リパスジル)
- 1日2回1滴点眼。
- Rho-associated coiled-coil kinase(ROCK)という酵素を阻害することで、線維柱帯流出路からの房水流出を促進
- 比較的最近登場した薬で、結膜充血(目が赤くなる)の副作用があり。
- 点眼後の一時的な症状であることを事前に説明しておくと、患者さんに安心。
- EP2受容体作動薬:エイベリス®(オミデネパグイソプロピル)
- 1日1回1滴点眼。
- プロスタグランジンの一種であるEP2受容体を刺激することで、線維柱帯流出路からの房水流出を促進
- 比較的新しい薬
- PG関連薬と同程度の眼圧下降効果を持つが、眼の周りへの副作用が少ないと言われている。
- 「白内障手術を既に受けた・近いうちに白内障手術を受ける可能性がある患者」には禁忌
- 炎症性眼疾患にも慎重投与
- タプロスとも併用禁忌(ほかのPG製剤も)
- 他の薬で効果が出ない・副作用や併用の問題で他の薬が使えない時に
ここが重要!緑内障の服薬指導3つのコツ
各薬剤についての注意以外にも、服薬指導では次の3つに気を付けましょう。
「生涯にわたる治療」であることを丁寧に伝える
初めて緑内障と診断された患者さんは、「点眼はこれから先ずっと必要」と言われて気分が落ち込んでいますよね。
帰宅後にネット検索などで調べることが多いでしょう。
そこでこういう文章が出てくるわけです。
「「緑内障は、日本の失明原因の第1位である」」
事実ではあるのですが、このような文章を発見したら絶望的な気持ちになると思いませんか?
失明について疑問や不安を訴えられたら、
現代では、早期に発見して適切に治療を行えば、生涯視野と視力を保てる病気といわれている。
医師の指示通りに点眼治療を続けていれば、失明はあまり心配はない
自覚症状がなくても毎日点眼を続けることが重要
副作用があった場合は、医師に相談して別の薬に変えてもらう選択肢がある
とにかく継続が重要
患者さんに寄り添いつつ、安心して治療を続けてもらえるように声掛けしましょう。
以下安心してもらうための詳細です。
- 緑内障は、日本の失明原因の第1位であることは事実。
- 緑内障は患者数が非常に多い(40歳以上の約20人に1人、60歳以上では約10人に1人)
- 患者数が多いため、失明に至る割合が低くても、結果として全体の失明者数に占める緑内障の割合が最も高くなるから
- 早期に発見し、適切な治療を継続すれば、失明に至る可能性は高くない。
点眼の正しい方法と順序を具体的に指導
複数の点眼薬がある場合は、「5分以上間隔を空けてください」と伝えましょう。
刺激の少ない薬剤(防腐剤なしのタプロスミニなど)や水溶性薬剤が先
懸濁性点眼剤やゲル化剤(リズモンTGなど)は最後に
副作用について事前に説明
出来るだけ副作用を抑えたり、患者さんが不安にならないようにあらかじめ説明しておきましょう。
- PG製剤
- 目の充血や、まぶたの色素沈着
- 対策:寝る前点眼・点眼後よくふき取る・洗顔など
- ベータ遮断薬
- ドライアイ(涙液を減らす作用あるため)、全身作用(脈拍の減少、気管支喘息の悪化、倦怠感)
- 対策:点眼後、1~5分間、目頭を指で押さえる→全身への吸収を減らす
- 炭酸脱水酵素阻害薬
- 口の中の苦み
- 点眼後目頭を押さえる。口をゆすぐなど
眼科での薬局復帰におすすめの本
面接をクリアして、眼科に復職が決まったら、専門書でさらに詳しい知識を付けましょう。
書籍を使ったおすすめの勉強法は、簡単なものから先に読んでいくことです。
読む順番は
- 一般向けの簡単なもの
- 薬剤師向けの本
- 医師向けの専門書
この順で読んでいくことで、次のように効率的に理解が進みます。
- 患者さんの不安や疑問、分かりやすい表現を知る
- 詳しい薬剤知識と服薬指導のポイントを頭に入れる
- 医師の処方意図や病院での処置について知る
一般向けの眼科本はこちら↓
薬剤師向けの本ならこちら↓
医師向けの専門書はこちら↓
まとめ
- 病態
- 眼圧(目の硬さ)が高くなり、視神経を圧迫して視野が徐々に狭くなる。
- 一度失われた視野は元に戻らないので、生涯にわたる継続的な治療が重要。
- 早期に発見して適切に治療を行えば、生涯視野と視力を保てるといわれている。
- 正常眼圧は10~21mmHg。
- ベースライン眼圧(治療を開始する前の眼圧)から、20~30%以上の眼圧下降を目指すのが一般的。
- 眼圧が正常範囲内でも視野障害が進行するタイプの緑内障もあり、正常眼圧緑内障と呼ばれ日本人に最も多いタイプ。
- 治療
- 第一選択薬はプロスタグランジン製剤が単独で処方される。
- 効果が不十分な場合は、2種類目・3種類目と追加あるいは種類を変更して目標眼圧を目指す。
- 点眼薬による眼圧のコントロールが難しい場合に、レーザー治療や手術が検討される
- PG製剤
- 代表的な薬:
- キサラタン(ラタノプロスト)
- ルミガン(ビマトプロスト)
- タプロス(タフルプロスト)※タプロスミニ(防腐剤を含まないのでドライアイ患者によい)
- トラバタンズ(トラボプロスト)
- レスキュラ(イソプロピルウノプロストン)1日2回
- 用法用量: 1日1回1滴点眼。
- ポイント:
- 房水(目の中の液体)の排出(ぶどう膜強膜流出路)を促して眼圧を下げる。
- 一日一回の点眼で、患者さんの負担が少なめ。
- 副作用として、まぶたや虹彩の色素沈着、まつ毛が伸びる。点眼後洗顔するとよい。
- 最も眼圧を下げる効果が高い
- 代表的な薬:
- β遮断薬
- 代表的な薬
- チモプトール(チモロールマレイン酸塩)、リズモンTG(熱応答ゲル1日1回冷蔵保存)
- ミケラン(カルテオロール塩酸塩)など。
- 用法用量: 基本は1日2回1滴
- ポイント
- 房水の産生を抑えて眼圧を下げる。
- 気管支喘息や心臓疾患のある患者さんには使えない場合がある。
- ベータ遮断薬、抗不整脈薬は併用禁忌
- テノーミン(アテノロール)、セロケン(メトプロロール)、インデラル(プロプラノロール)、アーチスト(カルベジロール)など
- ワソラン(ベラパミル)、ヘルベッサー(ジルチアゼム)、ジゴシン(ジギタリス製剤)など
- 内服薬や持病について医師に伝えたか&薬局でも必ず内容確認
- 代表的な薬
- 炭酸脱水素酵素阻害薬:
- 代表的な薬
- トルソプト(ドルゾラミド)
- エイゾプト(ブリンゾラミド)
- 1日2~3回1滴点眼。
- 房水の産生を抑え、眼圧を下げる。
- 点眼後に口の中が苦く感じる副作用がある。
- 薬剤に特有の強い苦味があり、鼻や口に流れることで苦み→「問題はない」と伝える
- すぐ瞬きをせず、一分ほど目をとじておく
- 点眼後目頭を指で押さえる
- 苦みがあれば口をゆすぐ
- 代表的な薬
- α2作動薬:アイファガン(ブリモニジン)
- 1日2回1滴点眼。
- 房水の産生を抑え、ぶどう膜強膜流出路からの房水流出を促進。
- 眠気やめまい、血圧低下などの副作用に注意。
- 高齢者への処方では、点眼後の様子を尋ねてみる。
- ROCK阻害薬:グラナテック(リパスジル)
- 1日2回1滴点眼。
- Rho-associated coiled-coil kinase(ROCK)という酵素を阻害することで、線維柱帯流出路からの房水流出を促進
- 比較的最近登場した薬で、結膜充血(目が赤くなる)の副作用があり。
- 点眼後の一時的な症状であることを事前に説明しておくと、患者さんに安心。
- EP2受容体作動薬:エイベリス®(オミデネパグイソプロピル)
- 1日1回1滴点眼。
- プロスタグランジンの一種であるEP2受容体を刺激することで、線維柱帯流出路からの房水流出を促進
- 比較的新しい薬
- PG関連薬と同程度の眼圧下降効果を持つが、眼の周りへの副作用が少ないと言われている。
- 「白内障手術を既に受けた・近いうちに白内障手術を受ける可能性がある患者」には禁忌
- 炎症性眼疾患にも慎重投与
- タプロスとも併用禁忌(ほかのPG製剤も)
- 他の薬で効果が出ない・副作用や併用の問題で他の薬が使えない時に
- 服薬指導のポイント
- 自覚症状がなくても毎日点眼を続けることが重要
- 定期的に通院して医師の指示通り点眼していれば、失明の可能性は低い
- 複数の点眼薬がある場合は、5分以上間隔を空ける。
- 刺激の少ない薬剤(防腐剤なしのタプロスミニなど)や水溶性薬剤が先。
懸濁性点眼剤やゲル化剤(リズモンTGなど)は最後 - PG製剤
- 副作用:目の充血や、まぶたの色素沈着
- 対策:寝る前点眼・点眼後よくふき取る・洗顔
- β遮断薬
- 副作用:ドライアイ(涙液を減らす作用あるため)、全身作用(脈拍の減少、気管支喘息の悪化、倦怠感)
- 対策:点眼後、1~5分間、目頭を指で押さえる→全身への吸収を減らす
- 炭酸脱水素酵素阻害薬
- 副作用:口の中の苦み
- 対策:点眼後目頭を押さえる。口をゆすぐなど
いかがでしたか?
これで基本的な緑内障の服薬指導はできるようになりますよ。
眼科に復職が決まった時には、必要に応じて詳しい所を掘り下げていってくださいね。
次回テーマは「アレルギー性結膜炎」です。