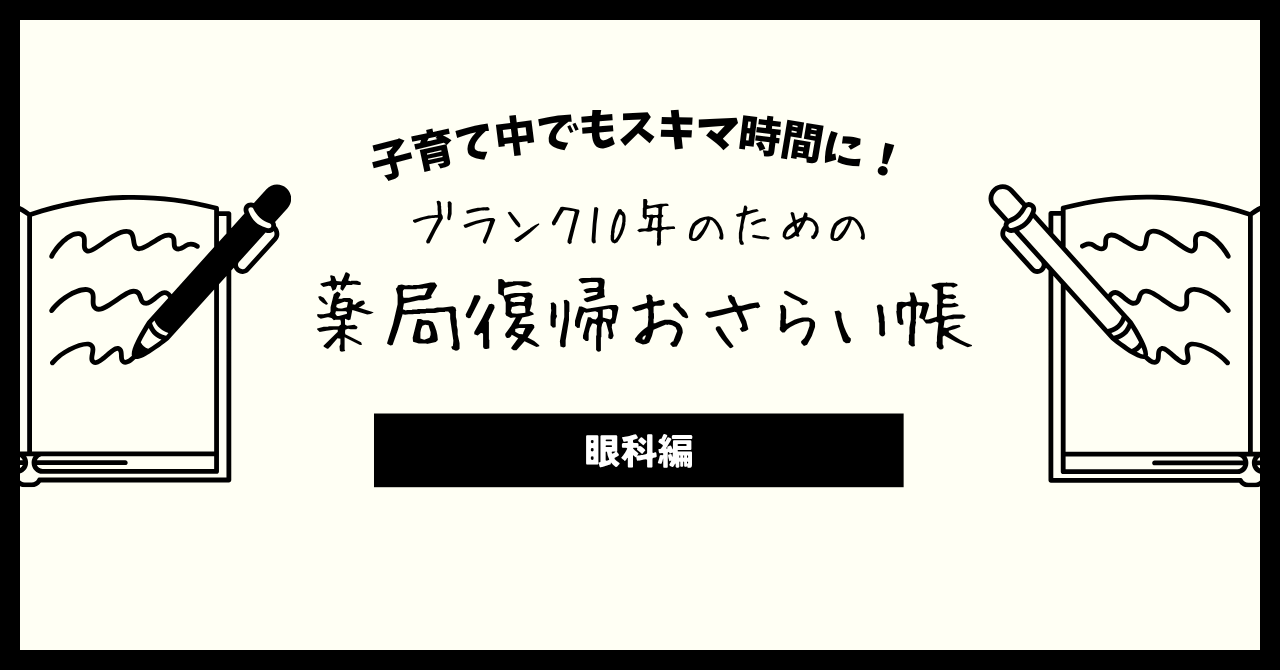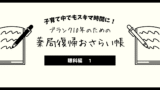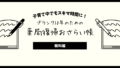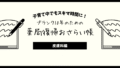こんにちは!
結婚出産育児で10年プラスαのブランクを乗り越え、薬局復帰を果たしたみのりママと申します。
今回の「薬局復帰おさらい帳」【眼科編8】では、患者さんに質問されがちな点眼剤の使い方について特集します。
点眼剤の使い方の基本・複数併用時の注意など服薬指導のコツ
眼科の門前薬局に即効で役に立ちますので、ババっと復習してさっそく現場で活用しましょう!
「ブランクが長いから復職が不安…勉強に身が入らない!」ママ薬剤師さんならこちら↓
復習を始める前に!最短で復帰するための行動プラン
眼科の門前薬局に応募は済ませましたか?
最短で復職を果たすには、「期限」を設定することが大切です。
まずは、気になる眼科門前薬局の求人に応募し、面接日を1〜2週間後に設定しましょう。
このゴール設定が、あなたのやる気をキープさせ、効率よく学べるようにしてくれますよ。
まだ応募をしていないなら、この勢いで気になる求人に応募してみましょう。
まずはここから!点眼剤の「種類」と「振る?振らない?」問題
患者さんからの質問が多い、薬液の特性に関する知識を整理しましょう。
- 水性点眼剤
- サラッとした液体。最も多いタイプ 。
- 振らない!
- 振ると泡立ってしまい、適量が点眼できない。
- 懸濁性点眼剤
- 白く濁っている(粒子が沈殿している)タイプ 。
- 使用前にしっかり振る!
- 例:ムコスタ点眼液
- 用事溶解型点眼剤
- 薬剤の安定性の問題などにより 、使用直前に2つの製剤を混合する 。
- 使用期限に注意!
- 薬剤ごとに溶解後の保管方法・使用期限が違うので注意。
- 溶かさずに溶剤だけ投薬してしまうミスなどがありがち!
- 例:カタリン、ベストロン
- 眼軟膏
- 油分を含み、効果が発現するまでゆるやかで、長時間作用
- 他の点眼剤の吸収を妨げるため、最後に点眼する
- 視界がぼやけることがあるので、就寝前適用がよくある
- 例:タリビット眼軟膏
忘れたままだと調剤ミスにもつながりやすいです。
復帰したら在庫の点眼剤を中心に確認しておくと、さらに安心ですね。
基本の「き」!正しい点眼手順と意外とやりがち?NG行為
患者さんが間違えやすい「点眼後のNG行動」については、初回に必ず確認しましょう。
基本的な点眼方法は、初回にさらっとメーカーのチラシなどを使って説明します。
私は、患者さんが高齢もしくは低年齢の場合は、次回以降に「正しく使用できているか、困ったことがないか」確認するようにしています。
やらないで!点眼後のNG行動
私は、初回の患者さんにはさらっとお話してます。
- まばたき禁止
- 無意識にやりがちなので要注意
- まばたきによって薬液が目から鼻に流れ出てしまう
- 目を閉じて1分以上待つとよい
- 容器を近づけすぎない
- 容器の先が瞼やまつげに触れないように注意する
- 雑菌が入って点眼液が汚染
基本の点眼方法
基本的な方法はこちらです。
- 石鹸と流水でしっかり手洗いする
- 下まぶたを軽く引き 、1~2滴を確実に点眼
- そのまましばらく(1~5分)まぶたを閉じる
- または涙嚢部(目頭のやや鼻より)を指先で軽く押さえる 。
容器の先がまつげやまぶたにつかない「げんこつ法」はこちら
げんこつ法
- 点眼剤を持った反対の手をげんこつにする
- げんこつをした瞼にあて、かるく引く
- 点眼剤を持つ手をげんこつに乗せ、指示された量を点眼する
おこさんに点眼する場合は、私はこんな方法をアドバイスをしてます。
お子さんにおすすめの点眼法
- 親子とも石鹸で手を洗う
- 子どもに仰向けで寝てもらう
- 親は頭の方に座るか、子どもの頭を膝にのせる
- こどもに「あっかんべー」をしてもらい、上をみて白目をむいてもらう
- めくれた瞼の内側に点眼する
複数点眼の「順番」と「間隔」を整理!
緑内障の治療や眼科手術後には、複数の点眼剤を使用することがあります 。
点眼剤の「順番」
複数の点眼剤を一度に使用する処方では、次のポイントに気を付けて患者さんにお話ししましょう。
- まずは患者さんにドクターからの指示を確認する。
- より効果を期待したい点眼剤を後から点眼。
- 点眼剤と眼軟膏を併用する場合には、眼軟膏を後に 。
- 水性点眼剤と懸濁性点眼剤(濁っているもの)では、懸濁性点眼剤を後から 。
- 特にドクターから指示がなければ上記を参考に指導。
点眼の「間隔」
少なくとも5分以上あけるようにお話します。
理由をきかれたら
「点眼間隔が短いと、最初の薬が洗い流されて効果が十分に得られない ことがあるからです」
とお答えしてます。
コンタクトレンズ使用時の点眼について
コンタクトレンズは目に負担になるので、基本的には症状がおさまるまでは外して眼鏡などを使うようにお願いしています。
まずは先生からどう指示されたか確認しましょう。
どうしてもコンタクトレンズを使用したい患者さんの場合はレンズの種類を確認します。
- ハードコンタクトレンズ
- →基本的には装着したまま点眼でも問題ない場合が多い
- ソフトコンタクトレンズ、酸素透過性ハードレンズ
- 基本的には外して点眼
- 点眼剤の成分が、角膜、コンタクトレンズ等に影響を及ぼす可能性あり
- 点眼剤によってはそのまま使用できることもあるので、その都度添付文書を確認する
- 再度装着する場合は、最低5分はあける
眼科や薬局によって、どう指導するかのマニュアルがあることもあります。
お勤め先が決まったら、念のため確認しておきましょう。
意外と知らない!点眼剤の保管と使用期限
点眼剤を保管する上で注意すべき点は、「温度」と「光」です 。
患者さんからはよく「冷蔵庫に入れるの?」と聞かれます。
基本をおさえてスムーズにお話しできるようにしましょう。
保管場所:「温度」と「光」
- 温度:
- ほとんどの点眼剤は、室温での保存でOK。
- 10度以下保存※凍結しない場所で
- リズモンTG点眼液0.5%(トラボプロスト)緑内障薬
- ジクロフェナク点眼液 NSAIDS
- キサラタン点眼液(ラタノプロスト)は開封前は冷蔵庫、開封後は室温でもOK
- 帰ったらすぐ冷蔵庫に入れるようお願いする(未開封)
- 車内や、真夏の室内では放置しないように注意
※後発品は個別に確認
- 「冷所保存」(15度以下)→ベストロン点眼用0.5%(セフメノキシム塩酸塩)※溶解後
- 冷蔵庫で保管する場合には、冷え過ぎによる「凍結」に注意
- 冷気の吹き出し口の近くや下段、チルド室は温度が低くなりやすいので避ける
- おすすめはドアポケット(振動に弱い薬は除く)
- 光
- 基本的に添付の小さな袋に保存して、直射日光が当たらなければOK
- 遮光保存が必須な薬は、特に出したまま放置しないように初回で指導する
- 遮光保存の点眼剤の例
- クラビット(レボフロキサシン)
- タリビット(オフロキサシン)
- キサラタン(ラタノプロスト)
- リズモンTG(トラボプロスト)
- パタノール(オロパタジン)
- アズレン
- パピロックミニ(シクロスポリン)
- リンデロン(ベタメタゾン)
- 付属の遮光袋は使い終わるまで捨てないように
- 直射日光や高温(車内など)は避ける
開封後の保管期限
- 一般的な点眼剤
- 開封後1か月を目途に使い切る
- 保存期間に注意が必要な点眼剤
- ベストロン点眼用0.5%(セフメノキシム塩酸塩)
- 溶解後、冷蔵保管・7日で廃棄(容器に溶解日を記載する)
- カタリン点眼用(ピレノキシン)
- 錠剤(※カタリンKは顆粒)溶解後、冷蔵保存、3週間以内に使い切る
- タリビット眼軟膏0.3%(オフロキサシン)
- 汚染されやすいので、開封後4週間(室温保存)
- ベストロン点眼用0.5%(セフメノキシム塩酸塩)
- 防腐剤フリーの一回使い切り規格(UD:ユニットドーズ)がある薬剤
- ムコスタ点眼液UD(レバミピド)ドライアイ治療薬
- ヒアレインミニ点眼液(ヒアルロン酸Na)角結膜上皮障がい治療
- パピロックミニ点眼液0.1(シクロスポリン)春季カタル治療薬
- 最初の1,2滴は必ず捨てる(容器の破片除去のため)
- 両目に点眼の場合はそのまま使用し、必ず残液は廃棄
目薬は何日でなくなる?一回に必要な滴数もチェック
この目薬は何日分出ているのか、患者さんに聞かれたことはありませんか?
基本を覚えておけば、簡単に答えられますので復習しておきましょう。
- 点眼剤の1滴は 約0.05ml
- まぶたの中に入る量は 約0.03ml
- 目薬は1滴で充分で、あふれるくらいである
- 一般的な点眼剤は 5mlなので100滴分
- 1日4回両目に1滴ずつ→100÷(4×2)=12.5日分
眼科での薬局復帰におすすめの本
面接をクリアして、眼科に復職が決まったら、専門書でさらに詳しい知識を付けましょう。
書籍を使ったおすすめの勉強法は、簡単なものから先に読んでいくことです。
読む順番は
- 一般向けの簡単なもの
- 薬剤師向けの本
- 医師向けの専門書
この順で読んでいくことで、次のように効率的に理解が進みます。
- 患者さんの不安や疑問、分かりやすい表現を知る
- 詳しい薬剤知識と服薬指導のポイントを頭に入れる
- 医師の処方意図や病院での処置について知る
一般向けの眼科本はこちら↓
薬剤師向けの本ならこちら↓
医師向けの専門書はこちら↓
まとめ
- 点眼剤の種類と注意すること
- 水性点眼剤
- 最も多いタイプ
- 振らない!(振ると泡立つ)
- 懸濁性点眼剤
- 使用前にしっかり振る!
- 例
- フルメトロン(フルオロメトロン)
- リンデロン(ベタメタゾン)
- ムコスタ(レバミピド)
- ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%「参天」
- ネバナック懸濁性点眼液(ネパフェナク)
- 用事溶解型点眼剤
- 散剤や錠剤を溶液に溶解してから使用
- 溶解後の使用期限に注意(溶解日を記載するとよい)
- 保管方法に注意(冷所保存)
- 例:カタリン、ベストロンなど
- 眼軟膏
- 他の点眼を併用時は必ず最後に
- 視界がぼやけるため就寝前処方が多い
- 汚染されやすいため開封後1か月を目安に
- 水性点眼剤
- 点眼方法
- まばたきは禁止(点眼剤が流れでてしまう)
- 容器の先が目などに触れないように注意
- 使用前に振る必要があるものに注意(それ以外は振らない)
- 10回程度しっかり振る
- UDタイプは下部のふくらみを指ではじく
- フルメトロン点眼液、オドメール(フルオロメトロン)
- ムコスタ点眼液UD
- ネバナック懸濁性点眼液(ネパフェナク)
- げんこつ法
- 目薬を持っていない方の手でげんこつを作る
- げんこつをした瞼にあて、かるく引く
- 点眼剤を持つ手をげんこつに乗せ、指示された量を点眼する
- 幼児への点眼
- こどもに「あっかんべー」をしてもらい、上をみて白目をむいてもらう
- めくれた瞼の内側に点眼する
- 点眼剤の「順番」と「間隔」
- まずは患者さんにドクターからの指示を確認する。
- より効果を期待したい点眼剤を後から点眼。
- 眼軟膏は最後に
- 水性点眼より懸濁性点眼剤は後に
- 少なくとも5分以上の間隔をあける
- コンタクトレンズ使用と点眼剤
- 基本的には外すが、処方医や薬局の方針を確認する
- ハードコンタクトレンズ(酸素透過性レンズ以外)は、基本的にそのままでもOKなことが多い
- ソフトコンタクトレンズ
- 基本的に外す
- 防腐剤や有効成分がレンズに吸着することがある
- 点眼剤によってはそのまま使用できることもあるので、その都度添付文書を確認する
- 再度装着する場合は、最低5分はあける
- 点眼剤の保管方法
- 温度
- ほとんどの点眼剤は、室温での保存でOK。
- 直射日光の当たる場所や車内への放置は避ける
- 冷所保存のものは凍結に注意→ドアポケットがおすすめ
- 10度以下保存
- リズモンTG点眼液0.5%(トラボプロスト)緑内障薬
- ジクロフェナク点眼液 NSAIDS
- 開封前のみ冷所保存(15度以下)→キサラタン点眼液(ラタノプロスト)
- 溶解後冷所保存(15度以下)
- ベストロン点眼(セフメノキシム塩酸塩)
- カタリン点眼用(ピレノキシン)
- 光
- 基本的に直射日光が当たる場所に置かない
- 添付の小さな薬袋に必ず入れる(特に遮光保存が必要なものは必ず説明する)
- 遮光保存
- クラビット(レボフロキサシン)
- タリビット(オフロキサシン)
- キサラタン(ラタノプロスト)
- リズモンTG(トラボプロスト)
- パタノール(オロパタジン)
- アズレン
- パピロックミニ(シクロスポリン)
- リンデロン(ベタメタゾン)
- 開封後の保管期限
- 基本的には開封後1か月を目途に使い切る
- 容器に溶解日や開封日を記載するとよい
- 保存期間に注意が必要な点眼剤
- ベストロン点眼用0.5%(セフメノキシム塩酸塩)溶解後、冷蔵で7日
- カタリン点眼用(ピレノキシン)溶解後、冷蔵で3週間以内
- タリビット眼軟膏0.3%(オフロキサシン)開封後4週間
- 防腐剤フリーの一回使い切り規格(UD:ユニットドーズ)
- ムコスタ点眼液UD(レバミピド)ドライアイ治療薬
- ヒアレインミニ点眼液(ヒアルロン酸Na)角結膜上皮障がい治療
- パピロックミニ点眼液0.1(シクロスポリン)春季カタル治療薬
- 最初の1,2滴は必ず捨てる(容器の破片除去のため)
- 両目に点眼の場合はそのまま使用し、必ず残液は廃棄
- 温度
- 点眼剤の滴数
- 点眼剤の1滴は 約0.05ml
- まぶたの中に入る量は 約0.03ml
- 目薬は1滴で充分
- 一般的な点眼剤は 5mlなので100滴分
いかがでしたか?
何度も読んで頭に入れれば、眼科門前の薬局だけでなくドラッグストアでも即効で役立ちます。
次回からは「皮膚科編」をはじめます。
一緒に現場復帰を目指して頑張りましょう!